911以前だからこそ貴重な「予言」
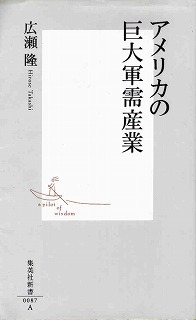
広瀬隆さんと言えば「東京に原発を」が有名だが、近年の著書はアメリカやヨーロッパの題材が多く昔とは趣が変わってきている。広瀬さんはアーマンド=ハマーの自伝を翻訳していて、古本屋で100円で買ったのだが、あまりに特大の本でまだほとんど読めていない。
数年前に「日本のゆくえ」という本を読んだが、ものすごい本だった。資料とその解説がほとんどなのだが、日本の政府の要人がどれだけ財閥や皇室とつながっているか、表に出てこない閨閥まで含めて延々と書き並べてあった。政治家や財閥の系譜図という、マスコミにはおよそ出てきそうにない図を見ていると、日本の政治が民主主義であるとはとても信じられなかった。
今回の本はタイトル通り、アメリカの軍事産業が建国以来どのように発展してきたかを膨大な資料をもとに解説したものである。誰が誰だかわからなくなるほど人名や肩書きの資料が多く、読みやすい本ではない。それでもだんだん引き込まれていくのは、延々と述べられる事実から描き出される本質の恐ろしさによるものである;
のちに初代財務長官となるアレグザンダー・ハミルトンが、フィラデルフィア随一の商人ロバート・モリスと手を組み、アメリカ国家最初の銀行として北米銀行 Bank of North America の設立を、議会で承認させることに成功した。モリスは、ただの商人ではなかった。独立宣言署名者のひとりで、アメリカ政府の借金財政を解消するため奔走した実質的な最高財務官であった。その一方で、ハミルトンを動かし、イギリスとアメリカの軍事物資の貿易で莫大な利益をあげていたのだ。"正直者"ワシントン将軍の妹ベティーの結婚相手も、ヴァージニア州の大地主で、戦場に武器を送りこんだ兵器屋フィールディング・ルイスであった。戦いながら、しこたまもうける。それが彼ら全員のルールとなっていた。(24−25ページ)
↑アメリカの建国以来の資本家と政治家のつながりが、このように延々と書き続けられる;
この新会社(Y注;ロッキード=マーティン)が二十世紀末から開発に最も力を入れてきたのは。統合攻撃戦闘機 Joint Strike Fighter と呼ばれる未来の戦闘機連隊である。契約を獲得すれば将来の総売上げ2000億ドルという法外なマーケットが見込まれたからである。22兆円の戦闘機連隊とは、どのようなものか想像もつかない。強大な軍隊国家アメリカが、いずれ宇宙人とでも戦おうというのか。誰とも分らぬ敵を想定して高性能の飛行部隊を着々とつくりあげてきた。(51−52ページ)
アメリカ国民は本気で22兆円を払う気があるのだろうか? わかっているのだろうか?
その一方で、ロッキードは次々とほかの会社を買収しながら、国外への兵器輸出にも手を打った。ブッシュ政権が92年に設立したアメリカ政府の軍需製品貿易諮問グループ議長にジョエル・ジョンソンが就任し、このグループのメンバー57人のうち54人を、主な兵器輸出企業の重役が占めた。クリントン大統領が就任してから、グループは95年4月に報告書を国務長官ウォーレン・クリストファーに提出し、紛争に関与する国に戦闘機を輸出してはならないとする制限禁止条項を、大統領やペンタゴンの恣意的な裁量で輸出できるよう、ほとんど骨抜きにしてしまったのである。このジョンソンこそ、国際航空宇宙産業協会副会長で、実は対等合併したばかりのロッキード・マーティンの代理人であった。(58ページ)
ロッキードは田中角栄にワイロを贈ったので有名だが、それはこの会社の活動の本質を表しているとも言える。あらゆる国の政府に力や金を加えて、自らの商品を売り込もうとしている。
(注;1998年の北朝鮮のテポドン発射事件について)これまで一度も報道されなかった事実は、その後、ずっと北朝鮮と日本と韓国を往復し、ミサイル問題と核疑惑の調査官という役割を果たした元国防長官ウィリアム・ペリーが、ミサイル防衛の主たる受注企業であるボーイングの重役室に入っていたということである。ペリーは、99年のユーゴスラビア・コソボ紛争に大量の軍用ヘリコプターを供給したシコルスキーの親会社ユナイテッド・テクノロジーズ重役のほか、巻頭に紹介した統合参謀本部副議長デヴィッド・ジェレミアが重役となった軍事投資銀行でも会長となっていたのだから、紛争地への銃器セールスを国防総省と統合参謀本部の幹部がおこなっていたことになる。(中略)ブッシュ大統領家は、黒船のペリー提督の子孫であるフロリダ州の大富豪ジョン・ホリデー・ペリーJrの近い親戚にあたり、民主党政権下で国防長官だったウィリアム・ペリーもその一族という関係にあった。(73−74ページ)
例のテポドン事件でさえ、ミサイル防衛という名目での、日本へのボーイングのミサイル売り込みに"ムダなく"利用されているわけだ。
これら軍需産業の相互の関係は、国際的な輸出市場を獲得する競争ではライバル同士だが、敵対して見えるアメリカとロシアと中国を問わず、互いに守ってきた業界ルールが三つあった。
第一は、国内外のメーカーを問わず、完全な競争の原則のもとで、兵器輸出はいかなる国に対しても自由に行ってよい。第二は、紛争の挑発と拡大に寄与する行為には、国籍を越えて協力し合う。第三は、国家が表面で掲げる外交政策とは無関係に行動してよい。つまり彼らは、敵国の兵器が自由に輸出されれば紛争が増え、同時に自社の企業利益が高まるという歴史の教訓を、理解し合っていた。(111ページ)
ブッシュ(注;父ブッシュ)はクリントンと争う92年の大統領選挙中に、マクドネル・ダグラスのセントルイス工場を訪れ、熱狂的な拍手のなか、「わが政府は、サウジアラビアへのF15戦闘機90億ドルの売却を認可します」と約束し、続いてゼネラル・ダイナミックスのフォートワース工場に赴くと、「みなさんが製造しているF16戦闘機の台湾への売却禁止を撤廃し、160機、総額60億ドルの輸出を認可します」と発表して、ここでも圧倒的な人気を博した。(169ページ)
要するに、アメリカの軍事産業は政府を「乗っ取り」、世界を股にかけて手段を選ばず兵器を売り歩いているのだ。企業と政府の人脈の重なり方を見ていると、政府と企業の癒着というより「同化」という表現が正しい。
『なぜ世界の半分が飢えるのか』(スーザン=ジョージ、朝日新聞社)という本を途中まで読んでいるが、こちらの本ではアメリカの食糧企業がいかに世界を支配しようとしているかが書かれている。もちろんそれは食糧企業とアメリカ政府が「同化」していることを示している。アメリカは民主主義のお手本だと言うが、外から見ると非常に純粋に資本の論理を貫徹しているように見える。
この本で最も考えさせられるのは、アメリカの国防予算のグラフである。ベトナム戦争が終わってからアメリカの軍事予算は逆に増大し始め、1990年にはベトナム戦争時の3倍以上である3000億ドルに達している(国家予算の中での割合は1985年をピークにして減少)。このグラフを見ていると、民主党が共和党にくらべて戦争に否定的であるということは全くない。現在のアメリカの軍事予算を組んだのは、ブッシュではなく前任のクリントンである。クリントン時代に軍事予算が伸び悩んだからといって、それは彼の手柄ではない。そうすると今回の選挙でも、果たして本当にケリーが勝つ方が戦争を避けるためによかったのかどうか判別できない。これだけ政府と企業が「同化」しているのだから、すべての大統領は操り人形であると言ってよく、党派の問題ではない。
今の二大政党制は、政府の本質を隠すためのうちわの茶番劇なのではないか。今までの政府と同化して利益を上げてきた企業と対決しようとする政治家は、決して政治の大勢に影響を与えることができない。 ……これは今の日本の状況と同じではないのか。日本はアメリカの後を追いかけて、政治のパターンまでアメリカと同じになってしまったように思う。一体今の日本の民主党が本気で、政治の本質で自民党と対決できるのか。アメリカの歴史と現状は、日本の未来を示唆しているのではないか。
広瀬さんの文章には、あまり余計な修飾語を入れない方がよい。どんなにそれが常識的なものでも、筆者の感じ方は一種の主観であって、このすざまじい事実の説得力を薄める。むしろ彼の本は純粋な資料としての価値が大きく、どれだけ資料として読みやすくするかに重点を置くべきようにも思われる。アメリカ南北戦争や東ティモール独立までの経緯など、これまでの私の知識を根底から覆すような記述も数多くあるだけに、広瀬さんの"主観"が入っているのは惜しい。しかしそうだからといって資料そのものの価値が変わるわけではない。政治学者だの評論家だのがたくさんいるのに、なぜこういう本を書ける人が少ないのだろうか。
この本は911事件の前に執筆されていて、沖縄の米軍基地縮小などを主張したブッシュJrに筆者はむしろ期待を寄せている。しかしその期待が裏切られたからといってこの本の価値は下がらない。むしろ、アメリカの戦争がまったく純粋に資本の論理において行われているということを証明しているこの本は、911事件の後に続くアメリカの行動を予言している。それだけに価値の高い本であり、読みにくいことを承知で一読を勧めたい。この時期にこういう本を平積みにしていた天神地下街の書店のセンスも賞賛したい。
引用しすぎであることを承知の上で、最後に日本についての一段落を紹介させてください(あかんかな);
日本人がこのようなアメリカの軍需産業の拡大を非難することはできない。満州事変を経て真珠湾攻撃から第二次世界大戦の敗北に至るまで、アジア各国でおこなった日本人の蛮行は、ヨーロッパにおけるナチス・ドイツ軍の行為と並んで、それまでの歴史に類を見ないほど極悪非道であった。第一次大戦では双方が利権争いに明け暮れたので、いずれも批判されるべきである。しかし二次大戦の日本とドイツの行動は、一分の理もなく、言い訳のしようがない。問題は、20世紀末に至るまで、日本の政治家と知識人、外交官、芸能人に至るまで、その国際的事実を恥じず、認めず、逆に否定する見解を語り続けてきたところにある。この状況が続く限り、アメリカの軍需産業が永遠に"真珠湾"を持ち出し、正しい存在となる。つまりロッキード・マーティン、ボーイング、グラマンの戦闘機を唯一正当化している理論は、日本人の言動そのものにある。筆者はそのような日本という国家から押しつけられる国籍を拒否し、一介の生物として以下に筆を進める。(108ページ)
ここに書いたように、戦時中の日本人の殺人・強奪・暴行等々の残虐行為にふれることを「自虐」と言う人がいるが、その言い分こそ正しい意味で「自虐」である。日本人が真に誇りを持とうとするなら、過去の犯罪を隠蔽しながら肯定するのは最悪の方法だ。愛国心を持ちたいのなら、日本人の歴史に汚点を残したこれらの事実をはっきり認識し、総括し、原因と責任をはっきりさせなければならないのに、今の状況はまるでダダをこねる赤ん坊並みである。教育基本法に愛国心を書き入れようとする彼ら自身の言動が、愛国心を育てる妨げになっているのだ。
筆者の言いたいことにはほとんど同感だが、彼も私も日本の現状に対する責任は「拒否」できない。彼は日本人としての責任を果たすためにこのような本を書いている。私には何ができるだろうか。(2004/12/4)