心理学で斬りたい放題
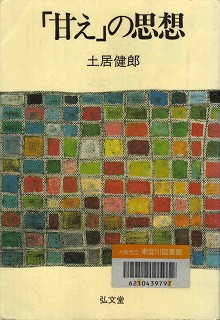
土居さんは『「甘え」の構造』で有名になった臨床精神科医で、大正9年生まれだからもうずいぶんお年の人である。『「甘え」の構造』を一度読みたいと思っていたが、図書館に行くとなかったので、代わりにこの本を借りて読んでみた。まとまったテーマに沿って書かれたものではなく、講演の記録や書評・雑誌に寄せたエッセイなどの寄せ集めであるが、テーマの難易にかかわらず非常に読みやすい。精神科医は「話を聞く」ことが最も重要な仕事だと言っているが、土居さんは患者の話を聞くことで、自らも話す訓練をしてきたのかと思わせる。様々なテーマや思想家を取り上げて、自らのつくった「甘え」の考え方とかみ合わせながら、ユニークな議論を展開している。
共産主義という夢はつい最近われわれの眼前から潰え去ったが、アメリカという夢は、たといそのために多くの人がつぶされるとしても、つぶれることはないだろう。ただアメリカという国家は今後あるいは衰えることがあるかもしれない。もちろん日本だってこの先どうなるかわかりはしない。しかし国家の盛衰とは別に、アメリカという人類の夢はなお生き続けるだろうと私は信じているのである。(78ページ)
日本人のアメリカに対する見方は人によってかなり差があるだろうが、アメリカの建国の理念である「自由」を否定するのは難しいだろう。それはかつて共産主義の理念である「平等」が世界中の多くの人間を魅了したのと似ている。共産主義の掲げる(実現されなかった)「平等」と、アメリカのめざす(他人の不自由の上に実現されている)「自由」のどちらかが一方的にすぐれているとは、私は思わない。土居さんの書いている「アメリカという人類の夢」とは、アメリカの現実でも、今のアメリカ政府が向かおうとしている方向でもなく、アメリカの独立宣言に謳われたような、より普遍的な「人間の平等の上に成り立った自由」ではないかと思う。
現代人の人間関係はさばさばしているというより、先に引用した漱石の言葉にあるように、むしろ「ばらばら」と言う方が当たっているからだ。もっとも個人主義なのだから、個人がばらばらでも文句は言えないはずだが、しかし問題はそのばらばらの個人が滅多に自立していないという事実である。したがって、そのような個人は社会の風の吹き廻し如何で、あっちにふらふら、こっちにふらふら、流されることになる。(93ページ)
土居さんはこの本では夏目漱石を多く引用していて、日本人の思想に対する思い入れの深さを感じさせるが、それは彼自身の留学体験が漱石や鴎外などのそれと重なって感じられるからかもしれない。上の文章にも、西洋から輸入された個人主義がどのようなものであるか、日本人にとって「自立していないばらばら」がどんなものか、漱石と土居さんの共有感覚のようなものがあるように読める。
現代の人間にとっての学習(勉強)とは、ばらばらであることを自覚し覚悟した上で自立する力、社会の風を感じながら自分の位置を見極めしっかり立つ力を養うためのものであろう。これは教える立場の人間にとっても重要な示唆である。
この本で特に興味深いのは、ゆとりについての文章である。土居氏はかつて余暇開発センターの会議の中で『ゆとり』という言葉を使うことを提唱し、「『ゆとり』という言葉をはやらせた元祖は、憚りながら私ではないかと思っている」(158ページ)と書いている。その"元祖"土居氏が考えるゆとりとは、
キリストが愛した人々の中にマルタとマリアという姉妹がいた。ある日キリストが彼女らの家を訪ねた際、マルタはもてなしに忙しく立ち働いていたが、マリアはキリストの話に聞き入ったまま、手伝うことを忘れていたらしい。ややあってマルタがそのことでキリストに文句を言ったところ、彼はこう言ったという。「お前は多くのことを思いわずらっているが、必要なものは一つだけだ。マリアはそれを選んだのだから、取り上げるわけにはいかない。」
このマリアは後に、キリストの死の直前、食卓についていたキリストのところに非常に高価な香油の入った壷を持参し、それを目の前で壊してキリストの頭に香油を注いだ人である。この時同席していた弟子たちはあまりの浪費におどろき、この油を売って貧しい人々に施せばよかったのにと言って彼女を非難した。するとキリストは、「貧しい人はいつでもいるが、私はいつまでもいない。この女がこのことをしたのは、私の死を予感してとむらいの準備をしたのだ」と言って彼女を弁護したという。
マリアにまつわる、以上二つの話は実に美しい。それはゆとりがある者とゆとりがない者の区別をあざやかに示している。それはまた、本当のゆとり、本当にパンを離れるということが、どのようにして可能となるかという点についても、多くを暗示しているように思われるのである。(162−163ページ)
この文章から私が読み取れるのは「何をするか自分で選べること」「本当に必要なもののためには"浪費"を惜しまないこと」というところである。イメージとしては『大学』である。何を学ぶか自分で選び、時間と費用を惜しまずにじっくり学ぶ。現実の大学がそうなっているとは限らないが、かつて大学の恩師は私に同じようなことを言った。効率や費用や競争原理に振り回されないで、最も必要な(大切な)ものを追求することが「ゆとり」であるならば、「ゆとり教育」というのは非常にゼイタクで理想的な考え方と言える。初等教育で考えるならば、「自分で選ぶ力」「本当に必要なものをとことん追求する力」を養うのがゆとり教育であると言えるだろう。
……すなわち、ゆとりとは、表にある価値と裏にある価値と二つあって、裏にある価値が表にある価値を超えている、実はそっちの方が高いということが見通されているときに生まれる心の落着き、それがゆとりなのです。だから、ゆとりというのは隠れているものです。私はゆとりがあります、などと見せびらかすことができるものではない。そう言ってまちがいないのではないかと思います。
最近の報道で、小学校か中学校で、ゆとりの時間をつくって、それをどう使うかで先生方が大変苦労した、という話がありましたが、これは当然のことですね。自由時間ならまだいいけれど、ゆとりの時間なんてナンセンスです。ゆとりの時間というのはおかしいが、時間のゆとりをつくることはできます。しかし、それには心のゆとりがなくてはならず、それは裏に隠れた価値があって初めてできる芸当です。だからこそ、ゆとりの時間といっても、何のことかちんぷんかんぷんわからなくなってしまうのです。(173−174ページ)
この本の別の文章で「顔は表を表し、心は裏を表す。うらやましいとかうらめしいとかいう言葉には、心の働きを表す意味が隠されている」という意味の記述があり、それと合わせると上の文はよく意味がわかる。心の中で価値を持つもの・点数や学歴(これが"表")ではかれないものを大切にすることが「ゆとり」であるなら、「点数で現れる学力が下がったからゆとり教育はまちがいだ」という論理はナンセンスである。
今までの文部科学省の政策がよかったかどうかは別にして、本当の「ゆとりのある教育」とは何なのか、目先の点数にとらわれる教育でいいのか、という議論は必要であろう。逆にそのような議論があれば、ゆとりの時間を本当のゆとりのために使うこともできるかもしれないし、政策として「ゆとり教育」から方向転換する場合にも、「"表"だけを見る教育でいいのか」という視点を持ち得ることができるだろう。学力の二極分化が問題になっているが、現在の最も大きな問題点は「ゆとり教育を謳ってきながら、子どもには(学力にかかわらず)ゆとりがなくなっている」ということだと私は考える。それは心のノートや愛国心や君が代のような「表」の方法でなんとかできるようなものではないことを、土居さんは語っているように思う。(『心のノート』を書いた河合隼雄氏は有名なユンギアンであるが、土居さんはそのような"どこか"に所属することを拒んでいるように見えるのも、何かの暗示のようで面白い。)
もう1つどうしても引用しておきたいのは、「転移」についてのフロイトの文章の紹介である。転移というのは心理学用語で、大ざっぱに言うと、クライアント(患者)が持っている心理状況がその担当医に直接心理的に伝わってしまうという概念だ。人間関係で悩んでいる患者が医者と話しているうちに、患者自身が悩んでいる人間関係を医者との間につくりあげてしまう、というようなことであろう。ここでは恋愛性転移−−患者が医者に恋愛感情を抱く−−について、
……フロイドがこれについて次のように書いています。転移の扱いをどうするかということについてお手本というものはどこにもないんだというわけです。……転移を避けてはいけないし、追っ払ってもいけないし、それを台無しにするようなこともしないように注意せねばいけない。またそれに分析者が答えようとしてはいけない。答えないでしかもそれをしっかりつかまえて、そしてそれをエトバス・ウンレアーレス、何か少し非現実的なものとして扱うのだと言うのです。さらに、分析者は患者から来るあらゆる誘惑に対して不死身であるように努めなければいけないとも言っています。
……この道ではなかなか玄人にはなれないということですね。いや、玄人になってはいけないんです。なぜか。マンネリ化するからです。マンネリ化したらもうだめなんです。素人であり続けることが、実は心理療法家、精神療法家の玄人たるゆえんなんです。……一番肝心なことは玄人であること、専門家であることに安住してはいけない、それぐらいに難しいことを私たちはやっているのだと申し上げたかったのです。(228−233ページ)
私なんぞがこんなことを書けた義理でもないが、これは教師と生徒の間にも言えることではないか。生徒が教師に恋愛感情を抱いた時、教師はどうするべきか。頭からはねつけるというのが一般論だろうが、上のように「答えないでしかもそれをしっかりつかまえて、そしてそれを何か少し非現実的なものとして扱う」ということはできないだろうか。私にはそんなことをする自信はないが、おそらく理想的な師弟関係と言われているものの中で、このような状態になっているケースがあるのではないか。マラソンの小出監督など、選手とこういう関係になっているのではないだろうか(非難しているわけではありませんよ、念のため)。
そして大村はまさんも書いていたように、教師にとってもマンネリ化は大きな敵である。教える技術を追求することについては玄人でなければならないが、人間関係や「学ぶ心」には玄人はない。多くのカウンセラーと会ってきたが、誠実なカウンセラーはみな「ああ、あなたはこのパターンですね」などという"あてはめ"をしなかった。患者一人一人との出会いがまったく新しい人間関係であることを、肝に銘じておられるのだと思う。それに比べると私は、子どもを見ていて「ああ、この子はこういうタイプだな」「このパターンだからこういうふうに指導しよう」というマンネリ的連想があまりにも多すぎる。教師にとって若さが大きな武器だというのは、マンネリになるほど経験がない時期の方が真摯に子どもと向き合えるということだろう。そういう真摯さがなくなるのは、簡単に言えば面倒くさいということか。テキストの問題を1年1年新しく解き直すように、子どもとの関係もマンネリ化しないように、よい意味での「素人」でいなければならない、ということだろう。……反省でございます。
それにしてもこういう本を読むと、心理学を志す生徒が多いのもわかるような気がする。優秀なカウンセラーは何より聞き上手であるが、書き上手でもあると思う。やっと『「甘え」の構造』も借りられたので、次はそちらを読みふけってみたい。(2005/1/31)