人間を解放するということ
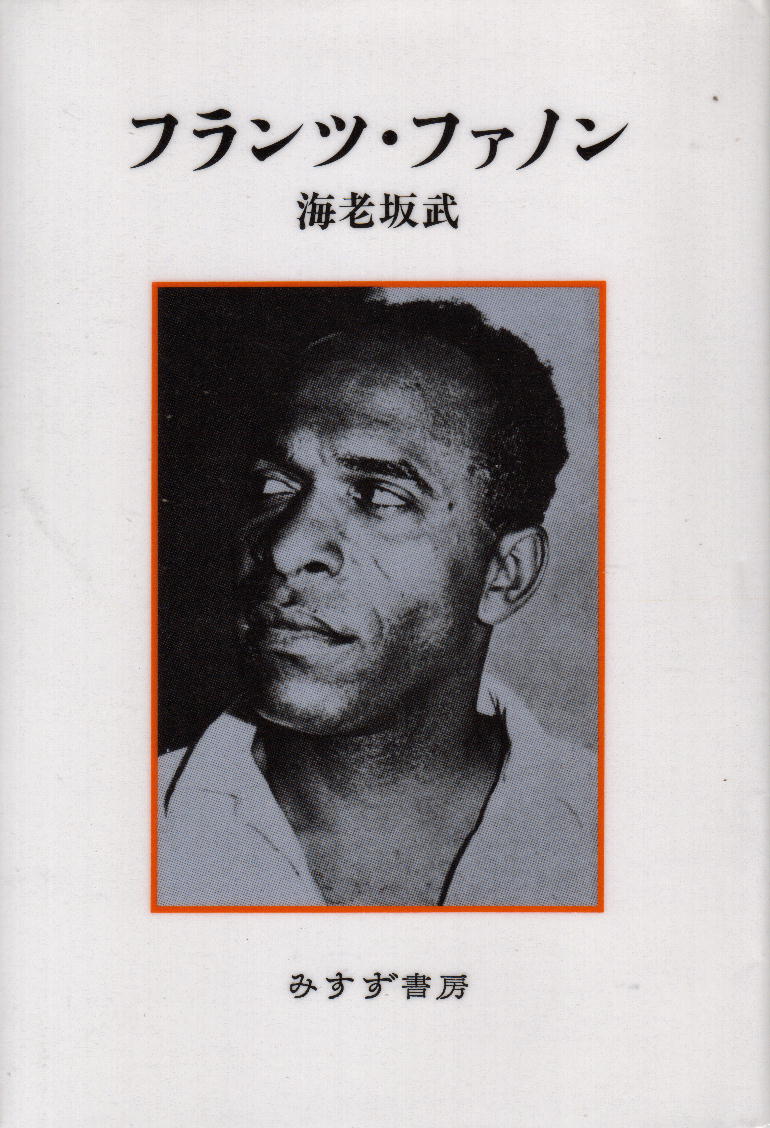
人間の苦しみを減らす方法には色々あるが、私なりに大きく分ければ、社会のあり方を変えるか、社会の中で生きている人間のあり方(考え方)を変えるかのどちらかになるだろう。前者は政治の問題であり後者は宗教や精神医学の問題であるが、この2つを統合して「社会を変える中でその中の人間を変革する」あるいは「社会と人間を同時に変える」という考え方もあり得る。もしそのような考え方が職業として成り立つとすれば、社会に働きかける宗教家、あるいは革命を志す精神科医というところだろうか。フランツ=ファノンはそのような立場にあった1人である。
フランツ=ファノンはカリブ海にあるマルティニック島で生まれた。
この島は17世紀にフランスの侵略を受け、原住民は30年ほどの間に絶滅した。サトウキビのプランテーションのためにアフリカから奴隷を"輸入"し、18世紀の間に白人1万人あまりに対して黒人と混血人が7万人あまりを占めるに至った。
19世紀半ばにフランス2月革命が起こり、この第二共和制の下で奴隷制は廃止された。農場主は奴隷の代わりとしてインドや中国から年季奉公人を"導入"し、これらの多様な人種が入り交じることでマルティニック人の皮膚の色は独特の多様性と複雑さを持つようになった。解放された黒人にも選挙権は与えられたが、総督の権限は絶大であり、本国の社会制度が様々な面で取り入れられ、マルティニック人は「同化の道をたどることになった」(81ページ)。
 このような場所で1925年に生まれ育ったファノンは、ナチスの傀儡であるヴィシー政権の下にあるフランス艦隊がこの島に駐留した15才のときに初めて「被差別体験」をし、駐留軍に対するレジスタンスに加わる。その後ドゴール将軍下のフランス軍に志願して南フランスで戦闘。第二次大戦後再度フランスに渡りリヨンで医学を学びながら政治活動に関わる。最初は歯科医になるつもりだったのが、途中から精神科医を志すようになった。一度マルティニック島に帰るが仕事がうまくいかず、すぐフランスに戻り精神科医として勤務。その後アルジェリア(当時はフランスの植民地)の病院に転勤し、ここでアルジェリア解放闘争と出会う。31才の時に病院を辞め、アルジェリア民族解放戦線(FLN)に参加する。以降医療活動に加えて、FLNのスポークスマン、機関紙の編集と執筆、駐ギニア大使としての地下軍事工作、そして独自の著作活動を行い、36才で白血病で亡くなっている。
このような場所で1925年に生まれ育ったファノンは、ナチスの傀儡であるヴィシー政権の下にあるフランス艦隊がこの島に駐留した15才のときに初めて「被差別体験」をし、駐留軍に対するレジスタンスに加わる。その後ドゴール将軍下のフランス軍に志願して南フランスで戦闘。第二次大戦後再度フランスに渡りリヨンで医学を学びながら政治活動に関わる。最初は歯科医になるつもりだったのが、途中から精神科医を志すようになった。一度マルティニック島に帰るが仕事がうまくいかず、すぐフランスに戻り精神科医として勤務。その後アルジェリア(当時はフランスの植民地)の病院に転勤し、ここでアルジェリア解放闘争と出会う。31才の時に病院を辞め、アルジェリア民族解放戦線(FLN)に参加する。以降医療活動に加えて、FLNのスポークスマン、機関紙の編集と執筆、駐ギニア大使としての地下軍事工作、そして独自の著作活動を行い、36才で白血病で亡くなっている。ジェットコースターのような彼の人生とその著作について解説しているこの本は、最初は読みにくかった。筆者が仏文学の専門家であるせいか、普段とは違う雰囲気の文章に振り回された。しかし1ヶ月ほどかけて読み返してみると、私にとっての大きなテーマがあちこちに散りばめられているのがわかった。
ファノンの人生の中での最初の大きな体験は、フランスでの白人からの蔑視であった。リヨンの公園で、小さい子からファノンはこう言われたという;
「ほら、ニグロ」「ママ、見て、ニグロだよ、こわい!」
そして母親は
「どうぞお気になさらないで。子どもなもんで。あなたが私たちと同じくらい文明人でいらっしゃるのがわからないんですよ」
ファノンは「その日、情容赦なく私を私のうちに閉じこめる他者、すなわち白人とともに外にいることができず」「私はこなごなに砕け散った。以下はもうひとりの私が拾い集めた私の破片である」と書いている。
同化政策のとられたマルティニック島で「フランス人」として育ち、その中でも経済的に恵まれた子ども時代を過ごしたファノンにとって、青年期に受けたこのような体験は、小さい頃から人種差別に"慣れて"いる人とは違った影響を及ぼすと思われる。小さい頃の体験が論理化されず感情や感覚として残ることが多いのに対して、ファノンは自らの体験を、その感情とともに論理によって分析し乗り越えようとした。それはまず"ネグリチュード"という思想に到達する。私なりに単純に解釈すれば、ネグリチュードとは白人優越主義に対抗するものとして「黒は美しい」「黒人であることに誇りを持つ」という考え方であり、このような考え方は運動として現在も存在する。
しかしファノンはここに留まらなかった。筆者によればネグリチュードを乗り越えるきっかけになったのは、サルトルの「黒いオルフェ」であるという;
「<ネグリチュード>は<ナルシシスム>の勝利であるとともにナルシスの自殺であり、文化や言葉やいっさいの心的事実をこえた魂の緊張であり、非知(non-savoir)の光り輝く夜であり、不可能なものを、バターユが刑苦(supplice)と名付けているものを故意に選択することであり、世界の直感的な受容であると同時に<心情の掟>の名による世界の拒否であり、矛盾する二重の請願、引き締まるような権利要求であるとともに、拡がり開かれるような寛大さであり、もっとも原本的な革命の投企と、もっとも純粋な詩とが、同一の源泉から湧き出ているのである」(132−133ページ)
難解な文章であるが、要するにネグリチュードがナルシシスムの勝利とか革命の投企とか「もっとも純粋な詩」であったとしても、最終的にはそれはナルシスの自殺であり「世界の拒否」であること、そこにファノンは行き当たったのだと思う。
私も(レベルは違うが)学生時代に差別について考えた。ボランティアで通っていた脳性マヒの人の施設で、障害を持った人とどのように接するか悩んだ。障害を持った人の詩に曲をつけて発表するわたぼうしコンサートも、発想としてはいわば一種のネグリチュードである。私はそこに5年間関わって、どうにも表現できないもどかしさを感じた。障害を持つ人にしか書けない詩というものがあるのか。突きつめれば私だって障害者ではないのか。差別を解消するために告発するのならまだわかるが、障害者の詩というだけでそこに価値を求めることに、本当に意味があるのか。……このような問いに悩まされた。今でも私にははっきりした結論がない。論理を振り回すことはできても、人間と人間の関わりという意味でのわたぼうしコンサートを否定することは、やっぱり私にはできない。
現在の日本で「日本人であることに誇りを持とう」「日本の文化は世界でも独特のものである」というような主張も、ファノンとは全く違う経緯をたどってはいるが、私から見れば一種のねじれたネグリチュードである。
私は疑いようもなく日本人だし日本文化の中で生まれ育ったが、そのことに特に誇りを持とうとか他国と比べて自慢しようとか思ったことがない。私にとって日本人であることは、誇りでも劣等感でもない(ムリに誇りを持とうとするのは劣等感の裏返しである)。それは私が日本人であることによって差別された体験を持たないからなのかもしれないし、差別する立場に立ち続けていることによってネグリチュード「以前」の状態に留まっているのかもしれない。
しかしこの国で本気で"ネグリチュード"を実践しようとすれば、実際には大きな困難が伴い、三島由紀夫のようになるくらいしか方法がない。日本には自らを誇るための真の独立も、日本人であることを誇るための歴史の清算も、日本文化を尊重し継承していくための政策も教育もまだ存在しない(岸田秀氏によれば日本は『アメリカの植民地』であり、そこまで言わなくてもアメリカから完全に独立しているとは言い難い。) これは同じく岸田秀氏によれば、日本が近代化する過程そのものがねじれていたことから起こる歴史的結果であり、私もそう考える。そのような意味で日本人とファノンに共通点があるとすれば、ファノンの生涯を通した主張は日本人の"ねじれ"をほどくヒントになるであろう。
ファノンは最終的にはネグリチュードを否定し、より普遍的な立場に身を置こうとしている;
……ファノンは、冒頭からその立場をはっきりとさせている。「真の問題は人間を解き放つことだ」と。「私は人間の身体をこそ熱したい」と。「一人一人の人間が、人間の条件に付随している普遍主義を引き受けることを目ざすべきである」と。つまりそれは、普遍主義、あるいは大文字の<人間>の立場であり、結論においては、さらに疑いのない形でそのことが再確認されるであろう。しばしば誤解されがちであるゆえにもう一度繰り返すが、彼は黒人の<白い仮面>あるいは黒人の<白い無意識>を否定して、逆に黒い皮膚の復権を訴えたのではない。そうではなく、白人に同化しようとする自己疎外を告発すると同時に、黒い皮膚に閉じこもりこれを価値化しようとする自己疎外に警告を発したのである。過去の奴隷になるな、歴史の虜になるな、輝ける黒人文明などということにこだわるな、黒い皮膚の色から価値を引き出そうなどと考えるな、と。彼は白−黒の二項対立から一歩先に出ようとしたのであり、その一歩先の立場とは、たしかに<人間>の立場としか言いようがなかったのであろう。(28−29ページ、下線部は原文では引用者による傍点、以下同じ)
しかし黒人にとって、白人への同化でも「黒い皮膚に閉じこもる」ことでもない選択肢とは何か。そのような文化は存在するのか。ファノンはそれを"革命"の中に求めている。
……だがファノンはもう一つ先に問を立て、これが重要なポイントである。解放闘争それ自体は文化現象か否か、と。そしてこの問に対して即座に然りと答える。組織的・意識的闘争は、「このうえもなく十全な文化的表現」であり、「闘争それ自体が、その展開において、その内的過程において、文化の多様な方向を発展させ、その新しい方向を描き出す」と。逆に言えば、豊かな文化の創造のためには、闘争の方法、内容、価値観、つまりはイデオロギーこそが重要ということになる。(279ページ)
つまりファノンにとって解放闘争とは、社会構造を変えることによって新しい文化を創造する行為そのものでもあるのだ。"新しい文化"についての具体的な記述はないが、私はたとえばプロレタリア文学のようなものを想像する。しかし社会主義を指向しなかったファノンの思い描く文化は、それとはかなり違ったものだろう。彼の主張の中には「頭脳と筋肉の協同」というような表現がよく見られる。頭でっかちにならず、誰かの肉体や知恵に頼るのでもなく、人間一人一人が自らの肉体と頭脳をになうことでつくり出す自分自身と文化;
「ヨーロッパはそのあらゆる街角で、世界のいたるところで、人間に出会うたびごとに人間を殺戮しながら、しかも人間について語ることをやめようとしない。このヨーロッパに訣別しよう」
「ヨーロッパの真似はしまいと心を決めようではないか。われわれの筋肉と頭脳とを、新たな方向に向かって緊張させようではないか。全的人間を作り出すべくつとめようではないか」(11ページ)
「……一つの橋の建設がもしそこに働く人びとの意識を豊かにしないものならば、橋は建設されぬがよい。市民は従前通り、泳ぐか渡し舟に乗るかして、川を渡っていればよい。橋は、空から降って湧くものであってはならない。社会の全景にデウス・エクス・マキーナによって押しつけられるものであってはならない。そうではなくて、市民の筋肉と頭脳とから生まれるべきものだ。なるほどおそらくは技師や建築家が必要になるだろう−−−それもときには一人残らず外国人であるかもしれない。だがその場合も党の地区委員がそこにいて、市民の砂漠のごとき頭脳の中に技術が浸透し、この橋が細部においても全体としても市民によって考え直され、計画され、引き受けられるようにすべきなのだ。市民は橋をわがものにせねばならない。このとき初めて、いっさいが可能となるのである。」(51−52ページ)
現在の日本がこのような方向に向かうことができるのだろうか。筆者は「そのような全的人間は、もちろん資本主義諸国に誕生する可能性はない」(54ページ)と書いている。またネグリチュードを脱する方法がファノンの提唱するものだけとは限らないだろう。しかし日本で、このことについて思想としても具体的な行動としても、提起されたものを私は知らない。これは私が本当に寡聞であるせいだろうから、日本人が「ジャパニチュード」を乗り越える方法について書かれたものをご存じの方は、ぜひ教えていただきたい。お願いします。
ファノンは精神科医としても「全的人間」を追求した。患者を拘束せず、機構療法や社会療法と呼ばれる治療法を試みた。
患者のうちに人間を見ること、狂気にもかかわらずでもなく、狂気ゆえにでもなく、「あるがままの人間」を見ること、これこそ精神科医ファノンにおける根本的姿勢でなくして何であろう。(174ページ)
……病棟ごとの全体ミーティングを週二回行って患者、職員との間にコミュニケーションの道をつけ、五三年のクリスマスのパーティが成功してからは月二回の「お祭り」を患者たち自身に組織させ、映画委員会、レコード委員会を設けて患者たちに映画やレコードを選ばせ、ときにはコメントをつけさせ、「われらの新聞」と題する週刊誌を発刊させ、作業療法を積極的に導入した(162ページ)。
これらの療法は、ヨーロッパ人女性患者に対しては大きな成果をあげたが、イスラム教徒男性患者に対してはうまくいかなかったという。言葉の問題などもあったのだろうが、この時点でファノンはまだ"ヨーロッパ人"であり、ヨーロッパ文化の中での治療しか思いつかなかったという面もあるだろう。筆者はこれをナイーヴなばかりのこの普遍主義に注目しておこう(163ページ)と書いているが、私から見ればこれはファノンの無知と楽観であって、西欧式の治療法を押しつけられたイスラム教徒にとってはたまったものではない。もちろんファノンはこのことに気づき反省の文章を書いているが、この経験が彼が後に"アルジェリア人"を指向するきっかけになったことは、容易に想像される。これは失敗が次の前進を呼ぶという事例の1つであろう。しかし単に「失敗から教訓を得て進歩する」というには、ファノンのその後の歩みはより過激でより本質的であった。これは彼の個人的資質なのか、彼の置かれた状況がそうさせたのか。両方の影響があることは間違いないのだが、ファノンの人生を考えるときこの点の分析が最も重要であると思われる。
フランス人医師として安定した生活を送ることもできたはずのファノンが、病院を辞め革命組織に参加するようになった動機は、以下のようなものであった;
……ファノンをして決定的な選択へ導いたのは、まず、憤激ではなかったかと思われる。……大量殺戮の場に居合わせたがために、肉親を殺されたがために、拷問を蒙ったがために、精神障害の新たな犠牲者たちが次々にブリダの病院に送り込まれてきた。『地に呪われたる者』の第五章において、彼はこれらの精神障害について冷静な筆致で症例を報告しているが、言葉の端々に憤激がほとばしり出ている。そしてこの憤激は、植民地主義の軍隊や警察に向けられていただけではなかった・被疑者に「自白血清」を注入したり、拷問の前後に強心剤やヴィタミンを投与したり電気ショックを与えたり、尋問に直接間接に手を貸すヨーロッパ人の医師たちにこそ彼は心からの憤激を覚えていたに違いない。彼らがつくり出した「ボロ布と化した人間」が、彼のところにまわされてくるだけにその怒りは激しいものであったろう。これら「医師でもある拷問吏」を告発しながら彼は、「すべての国の犯罪的医師は、死刑に処せられるべきだ」とさえ書いている。
 ……植民地戦争が始まる以前から、彼はすでに「植民地原住民を正しく治す」ことの困難を学会という場で訴えていた。戦争による弾圧の激化は、「植民地戦争性精神病」と呼びうる症状を彼に発見させた。この診断が正しいとするなら、治療の唯一の可能性は、植民地状況を消滅させ、その方向で植民地戦争を終結させることでしかありえない。そしてそのための唯一の手段が、解放闘争を勝利させることであるとするならば……ファノンは絶望の黒々としたとぐろの中に身を落ちつけるにはあまりにも健全であった。
……植民地戦争が始まる以前から、彼はすでに「植民地原住民を正しく治す」ことの困難を学会という場で訴えていた。戦争による弾圧の激化は、「植民地戦争性精神病」と呼びうる症状を彼に発見させた。この診断が正しいとするなら、治療の唯一の可能性は、植民地状況を消滅させ、その方向で植民地戦争を終結させることでしかありえない。そしてそのための唯一の手段が、解放闘争を勝利させることであるとするならば……ファノンは絶望の黒々としたとぐろの中に身を落ちつけるにはあまりにも健全であった。……「私の連れ歩く太陽」と書くときの光への意志、希望への賭け、生への活力、これこそファノンの健全さである。ラコスト宛ての辞表の最後の一句「人間に、すなわち私自身に絶望しないために……」はその意味において、恰好よさ、気どりと受けとってはならないだろう。(201−203ページ)
つまりファノンは、より本質的な意味で患者を「治す」ために、病院を辞めて革命組織の中に入ったのだ。その意味で彼は最後まで医師であり、誰よりも本質的な意味での医師であった。
筆者の"健全"という言葉を見るとき、今の私がいかに"不健全"であるかを思い知らされる。どんなに子どもと向き合おうとしても、私は塾講師として学歴差別を肯定して生活している。そしてほとんどの学校の教師は、子どもに対してどれだけ情熱的であっても、子どもに対して勉強の意味を正しく伝えられているとは言えない。
より本質的な意味での教師であろうとすれば、現在の教師としてのあり方を否定し、「全的人間」をつくるための教育を徹底的に志向する他ない。そういう教師が今の日本にいないとは思わないが、それは職業として公認された教員や講師とは限らない。何よりもまず社会を変えることを目ざす人間である。子どもに勉強を教えているから教師であるとは言えないのだ。このことについてもっと深く考え行動の基準を作る作業が、子どもを育てようとする人間にとっての最も大きな課題ではないだろうか。
筆者はこの本の最後で、現在の世界状況の中でどのように生きるべきかを論じている。それはファノンの思想を現在にどのように活かすかという思索である。
2001年9月11日、私はパリの友人の家にいた。事件の発生を知らされてテレビをつけると、二つの塔が次々に倒れていく映像が映し出された。私の最初の反応を正直に記すなら、「やった!」である。……私は9・11を報復として、反撃として受けとめたのだ。それは当然起こるに違いないことだった。それまでの30年くらいの間にアメリカが中近東で、アフリカで、中南米でやってきた犯罪の数々を考えれば、「想像もできなかった」などという反応は、知性の怠惰か偽善か計算、そのいずれかでしかなかった。(316−317ページ)
たしかあの時「やった!」という意味のことを言った日本の政治家がひどく叩かれていたと思うが、この言葉はおそらく世界中のあちこちで聞かれたことだろう。それがどんなに残酷であっても、思うことそのものは止められない。まして9・11よりはるかに残酷な現実に向き合ってきた人々にとっては、むしろこの感情は自然なものだったろう。私は筆者の感情が理解できる。この国がアメリカの"属国"であることが「やった!」という発言を封殺しているとすれば、それは日本全体の「知性の怠惰か偽善か計算」に結びついているのだ。私たちがテロ国家のテロ行為に手を貸し続けていること、したがって日本で「9・11」が起こることが、私たちの行為に対する"報復"であり"反撃"であることに気がつかないならば、テロを根絶することは不可能である。
ファノンの思想を受け継ぐならば、アメリカやヨーロッパ的「殺人思想」と決別し、かつてこの国を戦争に巻き込んだ"ジャパニチュード"をも乗り越えることで、はじめてこのようなテロの応酬を拒否し止める立場になり得る。これは普通に考えれば、ファノンのように革命を志向する思想にたどり着くだろうが、現在のこの国で革命を目指すのが難しいとすれば、個人はどうすればよいか。宗教による個人の精神の救済も、民族主義による○○チュードも意味をなさないとすれば、どこに出口を見いだせばよいか。
筆者は、民族にも宗教にも依拠しない者にとっての抵抗を考える。
……すぐにできることは、戦争という言葉をもはや使わずに国家テロリズムという言葉に置きかえることだ。「戦争反対」ではなく「国家テロリズム反対」と。(328ページ)
また、集団、個人によるテロを肯定しない一方で、テロを非難することを拒否している。
とりわけ、国家テロリズムの指導者たちが発するテロ非難に声を合わせることを拒否する。どんな場合にも、イエスかノーかの全体主義の壁に閉じこめられてはならないのだ。諾と言うことの拒否がノーなのではなく、否と言うことの拒否がイエスではないような言葉の空間を確保していくこと、民主主義の実践とはそういうことであるはずだ。……国家テロリズムの時代には、たぶん永久抵抗が要請されているのである。(329ページ)
最後の言葉は痛烈である。私たちは永久抵抗する勇気を持ち得るか。日々の安定した生活を賭して抵抗する動機を持ち続け得るか。人間は思想なしには生きられないが、肉体の安定と思想の保持のどちらかを問われたとき、思想をとる人間はどれだけいるのか。
それは比喩でない本当の「勇気」を問われることだ。歌や旗に敬意を表さない自由を守ることにすら大きな勇気が要求される今の日本で、私たちは本当に勇気のある人間でいられるか。欧米主義とジャパニチュードから脱却できない私たちに、生きる意味は見い出せるのか。ファノンが病院を辞めて革命組織に入ったときの"健全さ"を私たちは持ち得るのだろうか。国家が人殺しを肯定しオトナや子どもが自殺していく今の日本で、それらがそのままファノンの言う"不健全"さを表しているとしたら、私たちはファノンを目ざすべきなのだろうか。
暴力を肯定し革命に身を投じたファノンの考えが現代に通用するとは思わないが(暴力がいけないのではなく、国家の暴力に市民が対抗し得ない)、彼の持ち続けた"健全"さを現代にどう活かしていけるのか。私たち一人一人がささやかでも勇気を持ち、ほんの少しでも"健全"に生きていくことは可能なのか。子どもに対してファノンの求めた"健全"さを教え伝えていけるのか。それらの課題に向き合い問い続けるのが、彼の残した遺産を日本人が受け継ぐ正統な方法であるだろう。(2006/11/24)
※筆者の本書に対するコメントはこちら