抑圧としての勉強、または少年のパワー不足
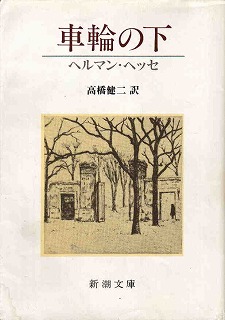
小さい頃に読んだ本の内容を、普通の人はどれくらい覚えているのだろうか。中学校までに読んだ本で、私が今でも鮮明に覚えているのは、『次郎物語』『お菓子放浪記(テレビでも見た)』あたりか。時間を忘れて読みまくった星新一のSFも、ボンヤリとしか覚えていない。『車輪の下』も中学生の時に読んでいたはずなのだが、内容はほとんど覚えていなかった。車輪の下という言葉の意味も当時知っていたはずなのに、すっかり忘れていた。
ドイツの片田舎で育った主人公ハンスは、勉強ができたので将来を嘱望され、猛勉強の末に神学校に入るが、神学校の生活で挫折を味わい学校を去る。村に帰ったハンスは工場の見習いになるが、仲間と飲みに行った帰りに川に落ちて死ぬ。神学校に入るまでの猛勉強そして神学校での経験と退学に至るまでの過程はヘッセ本人の実体験によるもので、自伝的小説とも言われている。
勉強ができる子が遊びから隔離されるというのは、日本でもよくあるパターンで違和感を感じない。当時のドイツでは、裕福でない家庭の子は、神学校から大学を出て神父になるのが唯一の出世の道だったらしい。この「東大コース」でどんな勉強をしていたのか書かれているのが興味深い。宗教、ギリシア語、ラテン語、ヘブライ語、数学…… ここで出てくる語学は聖書などの古典を読むためのもので、おそらく非常に解釈の難しい言葉が多いと思われる。また数学にしても、実用的な面より神学に転用可能な抽象的理論操作に主眼が置かれていただろう。ホメロスやリヴィウスなどの古典を読む話が随所に出てくるが、これも読書の楽しみというより、聖書や神の教えについて学ぶ助けとして位置づけられているようだ。
神学についてもほかのことと変わりはない。芸術といっていい神学もあれば、また他面、科学といっていい神学、少なくともそうあろうと努めている神学もある。それはいまもむかしも変わらない。そして科学的な人は、新しい皮袋のために古い酒を忘れ、芸術的な人は、数々の皮相な誤りを平気で固守しながら、多くの人に慰めと喜びを与えてきた。それは批判と創造、科学と芸術、この両者間の昔からの、勝負にならぬ戦いだった。その戦いにおいては、常に前者が正しいのだが、それはなんびとの役にもたたなかった。これに反し、後者はたえず信仰と愛と慰めと美と不滅感の種をまき散らし、たえずよい地盤を見つけるのである。生は死よりも強く、信仰は疑いより強いから。(50−51ページ)
非常に重いテーマをあっさり書き流しているようなこの一節は、筆者の神学への見方の現れだと思われる。ここでは「科学的」とされているが、私から見ると「革新的」と言っているように見える。若さの激情に流される者にとっては、生より魅惑的な死も、信仰より強く引きつける疑いもあるだろう。筆者の結論は、若さを押しつぶす社会の重さの実感ではないか。
思春期に入ろうかという年頃の少年たちがこのような勉強に長期間漬かって無事でいられるとは思えないが、人間の適応力というのはそのような時間の中でも無事でいられるように少年をつくりかえていくのだろう。しかしヘッセ本人がそうだったように、この物語でも3人が学校から出てしまっている。休み時間に池に落ちておぼれ死んだヒンディンガー、校則を無視し教師に抵抗したあげく脱走に失敗して放校処分になったハイルナー、そして最後の1人は神経衰弱になって家に帰された主人公のハンス。ハイルナーは情熱的な詩人で、訳者後書きによれば筆者はハンスとハイルナーの両者を自らのモデルとしているらしい。自らの心理を「分割」して描写するのは自伝的小説のテクニックかもしれないが、私から見るとやや物足りない。一人の人間の中に様々な面があるのが面白いので、分割することで内面の葛藤がかえって見えにくくなるようにも思える。もしかしたらヘッセは自らを分割したのではなく、学校の中での友人との関わりの象徴としてハイルナーをつくり出したのだろうか。積極的に反抗して放校処分になったハイルナーと、力尽きるように適応できなくなっていったハンスの様子を読んでいると、行動ではハイルナーの内面ではハンスの中に、筆者の思い入れを垣間見るようにもとれる。
……学校と父親や二、三の教師の残酷な名誉心とが、傷つきやすい子どものあどけなく彼らの前にひろげられた魂を、なんのいたわりもなく踏みにじることによって、このもろい美しい少年をここまで連れてきてしまったことを、だれも考えなかった。なぜ彼は最も感じやすい危険な少年時代に毎日夜中まで勉強しなければならなかったのか。なぜ彼から飼いウサギを取り上げてしまったのか。なぜラテン語学校で故意に彼を友だちから遠ざけてしまったのか。なぜ魚釣りをしたり、ぶらぶら遊んだりするのをとめたのか。なぜ心身をすりへらすようなくだらない名誉心の空虚な低級な理想をつぎこんだのか。なぜ試験のあとでさえも、当然休むべき休暇を彼に与えなかったのか。
いまやくたくたにされた小馬は道ばたに倒れて、もう物の役にもたたなくなった。(144−145ページ)
このような強烈な訴えの添えられた神学校時代の描写と比べると、その後の物語は少し歯切れが悪く感じられる。家に帰ってからの初恋と失恋、そして機械工として働き始めるあたりは、感傷的で美しい描写もあるが少々澱んでいて、ハンスの最期を予感させるものがある。なぜ彼は死んだのか、彼は機械工として出直した自分の人生をどう感じていたのか、自らの未来に対してどんな希望を持とうとしていたのか、私には読みとれない。主人公が死んだというより、筆者がハンスの人生を強引に終わらせたように見える。小説の名の通り、ハンスは車輪の下から抜け出せなかったということなのだろう。しかし実際のヘッセがそうであったように、このような車輪の重さだけで人間が簡単に死ねるとは思いがたい。おそらくこのような出世コースから外れた多くの若者は、ハンスのようにその心の傷を持ち続けながら、命を絶つことなく別の道を歩み続けたに違いない。"手っ取り早く"命を終わらせたハンスより、傷つきながら車輪から脱出し生き延びた多くの凡人に、私は興味がある。筆者は凡人ではなかったからそのような話を書き続けたくなかったのかもしれないが、つまるところ小説がここで終わっていては、車輪に轢かれたら命はないと言っているようなものだ。
まあ私に文学的素養がないのは明白なので、こんな読み方が正しいとも思われないが、描写の美しさや前半の文章のパワーがすばらしいだけに、なんとなくもったいないようにも感じてしまう。筆者は彼を取り巻く人々の「善意の抑圧」に対しての抗議としてハンスを殺したのかもしれないが、小説の中とはいえハラキリまがいの発想だとしたら、ドイツも日本も考え方は案外似ている……と言うことなのかな?
今の中学や高校で学ぶ諸々の科目がどれだけ「暗記」に傾いているのか、厳密に調べるのは非常に難しいだろうが、当時の勉強内容と比べればはるかに理論的・科学的側面が大きいことは疑いない。しかしだからといって我々が神学校の教師を無条件に批判できるわけではあるまい。否、当時の一握りの少年だけの悲劇と比べれば、今の日本の子どもを覆い尽くしている抑圧は比べものにならないほど大きい。現在の日本でも「信仰は疑いより強い」のだから。そして私のような受験勉強の専門家の多くは、多かれ少なかれ子どもに非論理的抑圧を与えている事実から逃れられない。私たちが「車輪」でなくなるためにはどうすればよいか。車輪が支えている車そのものを破壊するにはどうすればよいか。ヘッセの結論はいささか性急とも思えるが、だからといって現在問題が解決されているわけではないのだ。(2005/3/9)